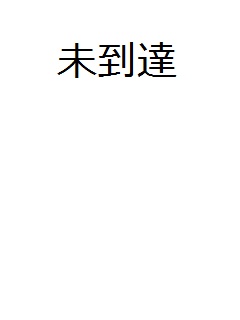神舞とは、5年目毎の旧暦8月1日から8日まで、三浦仮泊地と神舞場、大歳社前で行われる神事。平安時代の886年(仁和2)、東国東伊美郷(現在の大分県)の別宮八幡宮創建のため、京都の石清水八幡宮から分霊を受けて帰る途中、風波が荒れたので、船が祝島の三浦湾に避難し、錨を下ろして停泊した。そこには3戸の民家があり、産まれた子が、いずれも体格が整わず、嘆き悲しんでいた。これを見た勧請使一行は、哀れに思い、この地に、神霊を祀って(大歳神社)祈願するとともに、農耕の道を授けた。それ以来、産まれた子の体格も整い、生活も豊かになってきて、子孫が繁栄した。島民は、その神の恩に深く感謝し、毎年3月に、別宮八幡宮に貢物を捧げる儀式を行い、5年毎に、神船を飾り付けて神輿を迎え、祝島の氏神・宮戸八幡宮と大歳神社の3社合同の祭事を行うことにした。これが、神楽神事の始まりであると言われている。
海上13里を隔てた2村3社が合同で行なう、厳かで華やかな出船入り船の神事として、古式豊かな神楽舞いが繰り広げられる一大祭典である。
島民の集落は、練塀に囲まれた家波が続き、軒下まで積み上げられた塀は、敷地を囲むだけでなく住居の壁として現在も利用されている。
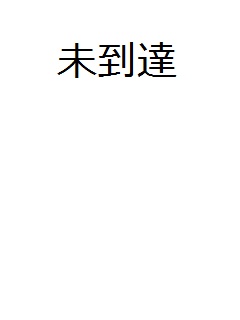
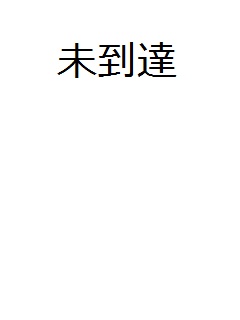
祝島(いわいしま)は、山口県熊毛郡上関町にある島です。
祝島は、周防灘と伊予灘の境界に位置しており、漁業を中心に栄えた島ですが、現在は過疎化が進んでいるようです。
祝島には、1日3便出ている定期船「いわい」を利用して上陸となります。
「練塀(ねりへい)」と呼ばれる石と土を積み重ね、漆喰で固めた独特の塀が特徴的です。
神舞神事は、4年に1度の開催で1,000年を超える歴史があります。
未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選【祝島の神舞と石積み集落】。